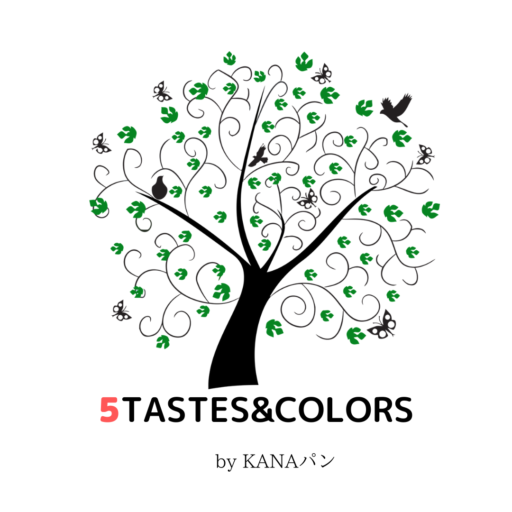5種の基本のスパイスとその効能。
スパイスは、100種類以上もの種類があって、それぞれに独特の味や香りや色があり、料理に深みを加えてくれます。
古くから、生薬として使われているものも多く、食欲増進や消化吸収、抗酸化作用、防腐、防臭作用など、さまざまな効能があり、健康や美容への効果が期待できます。
ただ、強い風味や刺激をもつものが多いので、個々の体質や健康状態によっては、使用法、適量を守って使用することが大切です。
ここでは、5種の基本スパイスとその効能、そして、使い方の基本を詳しくご紹介しています。
■シナモン ~カレーからお菓子まで幅広く『スパイスの王様』~

クスノキ科の植物で、10~15メートルに生長する常緑樹。一番外側の樹皮をはがしとって、細長く巻き、乾燥させたものがシナモンスティック、それをさらに、砕くと粉末になります。料理だけでなく、スイーツやコーヒーや紅茶などの飲み物などに使われています。八つ橋などの和菓子にも使われていることでおなじみですですね。
シナモンの効能
シナモンは、日本で最もポピュラーなスパイスの一つですね。性質は熱性で、カラダを温めて血流を促進することから、冷え性や動脈硬化の予防にも役立つとされています。他にも、
- 血管の健康維持
- 血糖値の安定
の効果もあります。
薬膳では、特に下半身を温めるので、腰痛の緩和、月経痛などの女性特有の症状にも効果があるとされています。ちなみに、生薬の桂皮とか桂枝とはシナモンのことで、漢方薬として服用したことがある方も多いかもしれません。頭痛や発熱、悪寒などに用いられます。
こんな体質の方は使い過ぎには気をつけて。
シナモンは、熱性の性質なことから、普段から、カラダに熱がこもりがちだったり、乾燥気味の方は、さらに症状が悪化してしまうことも考えられます。また、妊婦の方やのぼせやすい高齢者の方も食べすぎには注意です。
■クミン ~エスニックな香りとカレーに欠かせない辛味スパイス~

クミンシード
エジプト原産のセリ科の1年草で、種子がスパイスとして使われます。
強い芳香と苦味、辛味が特徴で、スパイスカレーのほか、チーズやソーセージ、パンなどにも使われます。最も古くから栽培されているスパイスの一つ。5000年以上も前から栽培されていて、古代エジプトでは、ミイラの防腐剤としても使われていたそうです。
ちなみに、クミン、コリアンダー、ターメリックの3種のスパイスと、さらに数種のスパイスをブレンドして、スパイスカレーになります。
クミンの効能
クミンの効能は、熱性の性質で、カラダを温め、食欲増進、消化促進、胃腸の膨満感の解消にも。また、殺菌効果もあります。
こんな体質の方は使い過ぎには気をつけて。
普段、カラダが熱っぽくて乾燥している体質の方、そうでない方もそんな症状がある時は、悪化させてしまう場合があるので、使い過ぎには気をつけてくださいね。
(小さなお子さまや妊婦の方は注意が必要です。)
クミンシードを使ったレシピ『クミンの肉じゃが』はこちらです。

おまけレシピ。『クミン塩』の作り方。
同量のクミンパウダーと塩を混ぜ合わせる。
唐揚げや、フライドポテトなどに振りかけて食べるのがおすすめです。
■コリアンダー(パクチー)~葉から種子まで栄養満点~

パクチーの花
せり科の一年草で、主に地中海沿岸、中東、北アフリカ、南西アジアが原産地です。
日本には、10世紀ごろ渡来し、コエンドロ、カメムシソウと呼ばれていました。その独特の香りと風味から、エスニック料理など、世界各地で広く、食用されています。生葉はパクチー、実を乾燥させたものが、スパイスであるコリアンダーです。

コリアンダー
葉の部分であるパクチーは、独特な味と香りで好みも分かれますが、コリアンダーは、爽やかでスパイシーなかんきつ系の香りが特徴です。スパイスカレーからデザートまで、幅広い料理で使用されています。
コリアンダー(パクチー)の効能
カラダを温め、胃腸を活発にし、食欲増進、消化促進効果があります。
葉の部分であるパクチーは、根までおいしく食べられます。ビタミンCやE、カルシウム、鉄などの栄養素が豊富で、抗酸化作用があり、デトックス、美肌作りにぴったりのハーブです。

☆おすすめレシピ『パクチーの簡単サラダ』はこちらです。
■ターメリック ~カレーの色の決め手のスパイス~

ショウガ科の多年草で、インドや熱帯アジアが原産。日本名はうこん、特に秋ウコンがターメリックです。地下茎の部分が主に利用され、黄金色をしています。香りがよく、苦味が特徴で、カレーのスパイスとして使われる他、染料やマスタード、チーズなど食品の着色に広く用いられています。鮮やかな黄色は、クルクミンと呼ばれるポリフェノールの一種です。
ターメリックの効能
カラダを温めるスパイスが多いなか、ターメリックは、寒性の性質で、カラダの熱を冷まし、血流を良くする性質があるので、高血圧の予防、改善、高脂血病の予防改善、血糖値を安定させる効果があります。また、肝臓へ働きかけ、肝臓の機能を回復、強化する効能ももち、悪酔いや二日酔い予防にも効果があります。
こんな体質の方は使い過ぎには気をつけて。
冷やす性質が強いターメリックは、普段、冷え性の方は、使い過ぎには注意が必要です。
また、妊婦の方も、使い過ぎには注意が必要です。
■カルダモン~清涼感のある香り『スパイスの女王』~

カルダモンは、ショウガ科の植物で、マレーシア、インド、スリランカ、ヒマラヤなどが原産です。高級スパイスのひとつで、実を日干し、または加熱して乾燥させたもの。スパイスの女王とも呼ばれる、清涼感のあるエキゾチックな香りが特徴です。スパイスカレーに使われるほか、クッキーなど、お菓子にもよく、使われています。
カルダモンの効能
- 胃腸を整える。消化液の分泌を促し、消化を促進し、胃もたれの予防や改善に効果があります。
- リラックス効果 清涼感のある香りが緊張やイライラを和らげ、疲労回復にも役立ちます。
- 発汗作用 血流をよくし、発汗を促す作用があるので、風邪のひきはじめに効果的です。また、脳の血流を増やすので、認知症予防にも期待ができるスパイスです。
- 口臭予防 強い香りが、匂い消しになるので、肉料理や、にんにく、アルコールを摂ったあとにカルダモンの種を噛むと効果的です。
スパイスの使い方の基本。~ホールスパイスとパウダースパイスを使い分ける。~
スパイスには、ホールスパイスとパウダースパイスの2タイプあって、それぞれに特性があります。料理の種類や調理法に合わせて、使い分けるといいですね。まず、使い方の基本を理解し、色々な料理に応用してみてください。
ホールスパイスは料理の最初に使う。
ホールスパイスとは、乾燥させた植物の果実や種、木の皮、葉など、そのままの状態のもの。香りが飛びにくく、長時間持続するという特性があります。
☆炒め料理に使用するには。
料理の最初に、軽く炒めて香りを油に移して使います。
☆煮込み料理に使用するには。
一緒に煮込んで、ゆっくりと香りを抽出させます。
ex.ローレル
パウダースパイスは料理の仕上げに。
パウダースパイスは、ホールスパイスを挽いて粉状にしたものです。ホールスパイスと比べ、味や香りが強い一方、香りが飛びやすいという特徴があり、特に加熱により、香りが飛びやすくなるので、料理の仕上げに使うのがおすすめです。熱や光、湿気に弱いので、早めに使い切るようにして、保管は密封容器に入れて冷暗所に保管するようにしてください。
では、みなさま✨
ステイヘルシーで、
今日もよい一日を🌈